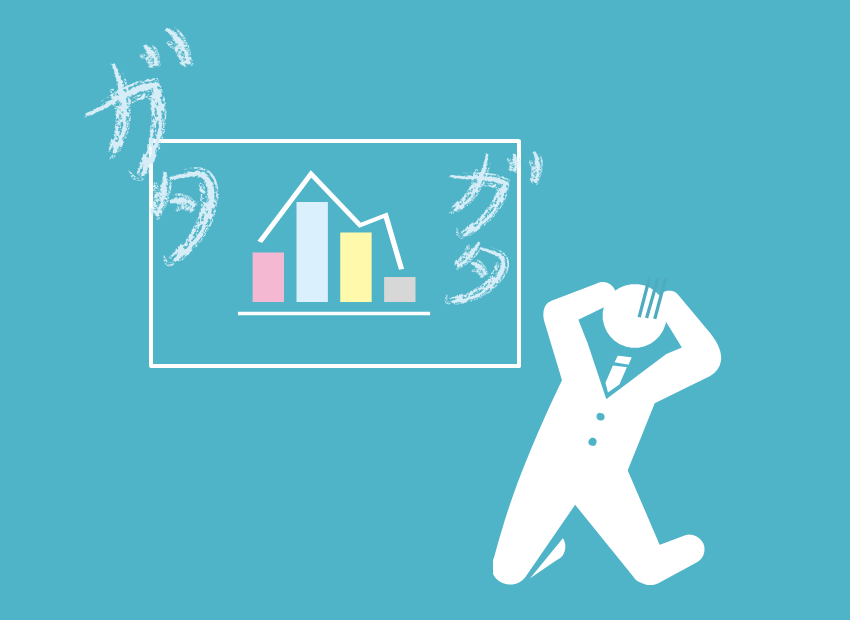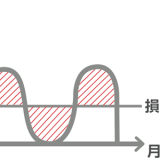Google検索で「Web制作」とキーワードを入力すると、下記のようなサジェストが表示されます。
- 「Web制作 儲からない」
- 「Web制作会社 なくなる」
- 「Web制作 オワコン」
また、Twitterにおいても「Web制作は儲からない」といった趣旨のツイートを複数みかけました。
果たして、Web制作は本当に儲からないのでしょうか。
また、Web制作は儲からないと言われる理由は何なのでしょうか。
Web制作会社が安定収益を生み出すにはどのようにすれば良いのでしょうか?
Web制作が儲からないと言われる理由
Web制作が儲からないと言われる主な理由は、下記の3つです。
- 参入障壁が低く、価格競争が起こりやすい
- 労働集約的型のビジネスであること
- 無料ツールなどの技術進化
それぞれの理由について詳しく解説していきます。
Web制作は参入障壁が低く、価格競争が起こりやすい

Web制作は個人で行う場合、自宅で開業でき、特別な設備など多額の初期投資も不要であり、パソコン1台とAdobe CCなどの利用料があれば事業を始めることができます。
そのため参入障壁が低いため、新規参入者が多く、価格競争が起こりやすいです。
また、後ほど記載するような無料でWebサイトを制作できるツールなどが進化していることも、参入障壁を低くしている要因です。
このように価格競争が起こり、受注単価が下がることが「Web制作が儲からない」と言われる1つの理由では無いでしょうか。
Web制作は、労働集約型のビジネスである

Web制作は、労働集約型のビジネスです。
下記が、労働集約型産業の意味ですが、簡単に説明すると、人間の労働力に頼っている業務の割合が高いビジネスのことです。
生産要素に占める資本の割合が低く、労働との結合度の高い産業のこと。労働者1人当りの設備投資額(=労働の資本装備率)の低いものを一般に労働集約型産業とよぶ。
労働集約型産業(ろうどうしゅうやくがたさんぎょう)とは? 意味や使い方 – コトバンク
Web制作では、営業、提案、ディレクション、デザイン、コーディングなど全ての工程に人間の労働力が必要です。サービスを必要とするお客様がいたとしても、対応できる労働力がなければ、仕事を受けることができません。
つまり、単価を変えずに売上を伸ばしていくためには、人員を増やし続けていくしかありません。
Web制作では、お客様に対してオーダーメイドのWebサイトを提供する場合が多く、その仕様により工数が変動します。
そのため、工数を予測して、Webサイトごとに見積もりが作成されます。
デザインの度重なる修正や、仕様変更などにより、見積もり工数をオーバーしてしまうと、利益が少なくなるばかりか、赤字になる案件が発生する可能性もあります。
このような労働集約型のビジネスであることが、「Web制作が儲からない」と言われる1つの理由では無いでしょうか。
無料ツールなどの技術進化

Web制作では、WixやSTUDIO、Jimdoなど、ノーコード(プログラミング不要)ツールが登場し、進化を続けています。
ITリテラシーの高い方であれば、これらのツールを活用して、簡単なWebサイトであれば作ることができます。
また、Canvaなどの無料デザインツールも進化を続けており、デザインの実務経験が無くとも、一定のクオリティの制作物が作りやすくなっています。
これらのツールの登場により、Web制作では下記のようなことが発生しています。
- Web制作会社に依頼せず、ノーコードツールを活用し自社でWebサイトを制作する
- フリーランスの方などが、ノーコードツールを活用して安価でWebサイト制作を提供する
このように、ノーコードツールの進化により、Web制作への参入障壁がさらに低くなり、その結果単価が下がると予測されることが、「Web制作が儲からない」と言われる1つの理由では無いでしょうか。
Web制作会社が安定収益を生み出すには、フロー型ビジネスとストック型ビジネスのバランスが重要
ここまで、「Web制作が儲からない」と言われる理由について考えてきましたが、Web制作会社は本当に儲からないのでしょうか?
正しくは、「ただ言われた通りにWebサイトを作るだけでは儲からない」では無いでしょうか。

Web制作を20年続けてきた弊社ですが、Web制作会社が安定収益を生み出すには、フロー型ビジネスとストック型ビジネスのバランスが重要だと考えています。
フロー型ビジネスにより短期間で単発的に収益を上げて、ストック型ビジネスを育てて収益を安定化させるというものです。
詳しく解説していきます。
フロー型ビジネスとは
まず、フロー型ビジネスとは、サービスを提供して単発的に収益を上げるビジネスモデルのことです。
言い換えると、売り切り型のビジネスです。Web制作会社では、受託制作がこれに当てはまります。
Webサイトは、頻繁にリニューアルするものではないため、受託制作のみで売上を上げるためには、営業を行ったり紹介を受けたりして多くの企業のWebサイトを作り続ける必要があります。
一方で、フロー型ビジネスは、デメリットばかりではなく、短期間で収益化できるというメリットがあります。
このようなフロー型ビジネスで収益を上げるためには、下記のような取り組みが必要です。
- Webサイト制作に独自性と付加価値を加えて、受注単価を高める
- Webサイト制作の業務効率化を図り、工数を削減する
- Webサイト制作に関連するサービスを提供し、顧客1社あたりの単価を高める
それぞれについて、詳しく解説します。
Webサイト制作に独自性と付加価値を加えて、受注単価を高める
BtoB企業特化、製造業特化、士業特化、採用サイト特化などのポジショニングを取り、それらについての専門的な知識やノウハウ、実績を蓄積し、提供するなどを行うことで、強い独自性を作り、価値を提供することです。
言い換えると、お客様にとって「このWeb制作会社以外は考えられない!」という状態を目指すことで、受注単価を高めることです。
強い独自性や付加価値があれば、価格競争に巻き込まれにくくなります。
Webサイト制作の業務効率化を図り、工数を削減する
受注単価を変えずに、収益を生み出すためには、コストを削減することが必要です。
Web制作は、労働集約型のビジネスであるため、工数を削減することがコスト削減に一番インパクトがあります。
制作フローを見直す、テンプレート化できる部分を見つけて同じことを繰り返さない、業務改善につながるツールの導入などを行い、工数を削減しましょう。
弊社は、依頼管理ツール「トコトン」だけでなく、修正依頼ツール「AUN」を提供しています。
AUNを活用すると、制作物の修正指示にかかる時間を約6分の1に短縮することが可能です。(弊社検証による)
削減できるコストと比較して、このような業務効率化ツールの導入を検討しましょう。
Webサイト制作に関連するサービスを提供し、顧客1社あたりの単価を高める
Webサイト制作のみをサービスとして提供する場合、せっかく契約に至り顧客との接点ができても、次回のWebサイトリニューアルまでには、約4~5年の期間が空くことになります。
突然ですが、マーケティング用語に「1:5の法則」というものがあるのをご存知でしょうか?
これは、サービスを新規顧客に販売するコストは、既存顧客に販売するコストの5倍かかるという法則です。
つまり、Webサイト制作という1つのサービスを複数の見込顧客に営業し続けるのではなく、既に取引があり信頼を獲得している既存顧客に対して、他のサービスを提供していく方が効果的ということです。
Webサイト制作に関連するサービスとして、例えば下記のようなものがあります。
- Webサイト更新代行
- Web解析
- Web広告運用
- SNS運用支援
- Indeed活用など求人に関する支援
ストック型ビジネスとは
ここまでフロー型ビジネスについて紹介しましたが、ストック型ビジネスとは何でしょうか?
ストック型ビジネスとは、定額または従量課金のサービスを提供して継続的に収益を上げるビジネスモデルのことです。
サブスクリプションビジネスとも呼ばれます。
Adobe CCやMicrosoft 365、Chatworkなど月額費用を支払うことで、サービスを利用し続けれるものがこれに当てはまります。
ストック型ビジネスのメリットは、一度新規顧客を獲得できれば、退会や解約が無い限り、毎月一定の売上が確保できることです。
弊社では、下記のようなストック型ビジネスを展開しています。
- Webサイト運用に特化した依頼管理ツール「トコトン」
- 修正指示/修正依頼ツール「AUN」
- Webサイト保守管理サービス

トコトンやAUNのようなクラウドツールは、開発に大きな初期費用がかかり、その後、保守や機能追加、Webサーバー、広告費などに継続してコストがかかります。
一定の利用ユーザーを獲得し、売上がコストを上回れば、極端な話、その後の新規ユーザー分が利益となります。
このようなクラウドツールを提供するメリットは、労働集約型のビジネスではないことです。
Web制作の場合、仮に10サイトを制作するのに仮に10の労働力が必要な場合、100サイトを制作するのには、100の労働力が必要です。つまりサイトを制作する分だけ比例して労働力が必要になります。
クラウドツールの場合は、10ユーザーにサービスを提供するのに10の労働力が必要な場合でも、100ユーザーにサービスを提供するのに、同じ10に近い労働力でサービスを提供することが可能です。
しかし、このようなクラウドツールは、開発コストが莫大にかかる一方で、利用ユーザーが増えるかどうかが読めない点に大きなリスクがあります。
それでは、何を行うべきかというと、Webサイトの保守・管理・運用サービスです。
お客様のWebサイトに定期的に手を加えて、より良い状態を目指すためのサポートを行うことです。
これは、自社の収益安定化のためだけではなく、制作したWebサイトをお客様に最大限活用していただくために必要不可欠なサービスです。
Webサイトの「保守・管理・運用」で安定収益を生み出す
Webサイトの保守・管理・運用サービスのプランは、一般的に定額課金のサービスと、従量課金のサービスに分かれています。
弊社が調査してみたところ、下記のように分かれていることが多いようです。
- サーバー・ドメインの管理
- データバックアップなど
- システムのアップデート
- 電話やメールによるサポート
- ページ修正
- 新規ページ追加
- 新規画像制作
- アクセス解析レポート(定額サービスに含まれる場合もあり)
その他、Webサイト保守・管理・運用サービスに含まれるサービス例は、下記の記事にまとめております。
 ホームページ管理・保守費用の内訳と相場とは?
ホームページ管理・保守費用の内訳と相場とは?
Webサイトの受託制作業務と並行して、Webサイト保守・管理・運用サービスの提案を行い、契約者数を増やしていくことで、収益の安定化を図ることができます。
Webサイトの保守・管理・運用サービスを提供する上で定めておくべきルール
Webサイトの保守・管理・運用サービスでは、通常のWeb制作受託案件とは区別した業務フローを定める必要があります。
保守・管理・運用に特化したルールや業務フローを作ることで、Web制作会社もお客様も互いにメリットを享受できます。
下記、5点について事前に準備してから、サービスを開始しましょう。
- 各作業の価格
- 担当者
- 依頼フォーマット
- 依頼管理ツール
- Webサイト保守契約
1.各作業の価格を定義する
まずは、Webサイト保守・管理・運用で発生する可能性のある作業を洗い出し、価格を明記した表にまとめましょう。
これにより、お客様は、事前に価格を把握できるので、受発注がスムーズになり、作業着手までのタイムラグが少なくなります。
2.サポート担当者を定める
いつ依頼が入って来ても対応できるように、サポート担当者を決めます。
兼務でも問題ありませんが、サポート担当者は、Webサイトの保守・管理・運用業務を優先するようにしましょう。
これにより、他の人は、受託案件に集中でき、会社全体の業務効率が上がります。また、特定の人が親身に対応してくれるので、お客様の信頼感も増します。
3.依頼フォーマットを指定する
依頼は、特定のツールでのみ受付け可能とし、窓口を一本化します。
また、依頼フォーマット(Excel等を利用)を併用すると、内容の齟齬や対応の遅れを削減できます。
4.依頼管理ツールを指定する
プロジェクト管理ツールやナレッジ管理ツールを利用して、これまでの依頼内容や、予算、作業時のやり取り等を記録しましょう。トラブル発生時には管理情報をもとに検証を行います。
情報をまとめておくことで、今後のサイトの方向性を計画する参考データとして利用し、Webサイトの将来を、戦略的に見通せます。
5.事前入金の保守契約をつくる
前払いで保守契約を結ぶようにすれば、相応の人員を動かせる資金を事前に調達できます。
事前に費用を頂くためには、保守範囲を明確にする必要があります。
Webサイトの保守・管理・運用サービスには、依頼管理ツール「トコトン」
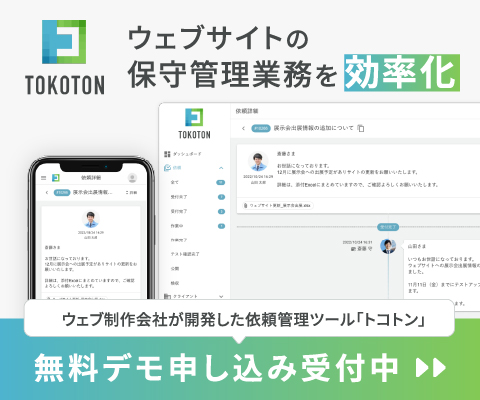
Web保守・管理・運用に特化したルールや業務フローを決めて、サービスを提供するためには、依頼管理ツール「トコトン」がおすすめです。
「トコトン」は、小規模案件に特化したプロジェクト管理ツールで、日々の細かい更新依頼の情報を一元化することができます。
下記のように、Webサイトの保守・管理・運用に特化した様々な機能を搭載しています。
- クライアント情報/契約内容登録機能
- プラン/サービス登録機能
- ステータス管理機能
- カレンダー型タスク管理機能
- ポイント機能
無料デモ体験の申し込みも受け付け中です。
詳しいサービス内容については、依頼管理ツール「トコトン」サービスサイトからご確認ください。