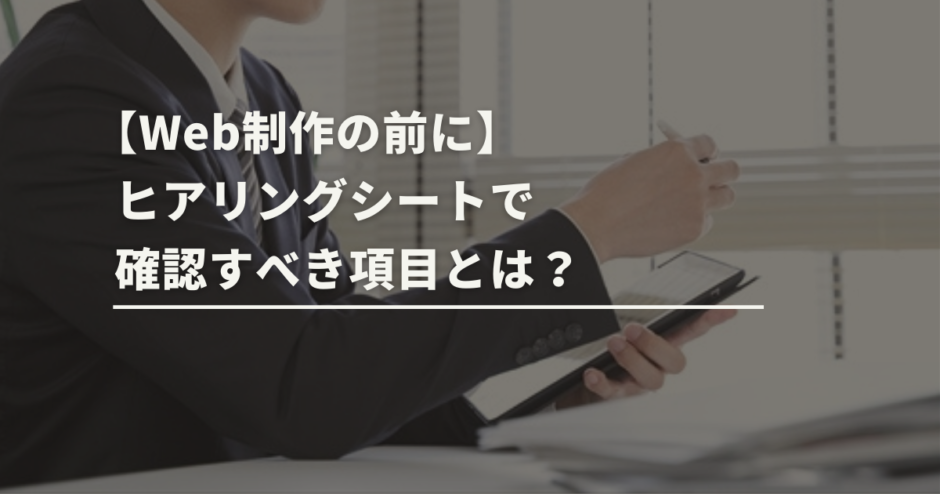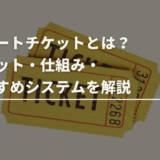Web制作を始めるうえで、最初に必要なのはクライアントへのヒアリングです。
このヒアリングをもとに、クライアントがどのような問題を抱えていて、Webサイトによってどのように課題解決を図っていくかを考えていきます。
今回は、ヒアリングの進め方や実際にどのような内容をヒアリングするのか、押さえておきたい基本事項について紹介いたします。
本記事で紹介しているヒアリング項目をシートにまとめたものを配布しています。
以下のボタンから資料をダウンロードしてご活用ください!
ヒアリングの目的
ヒアリングは、Webサイトの提案をする前段階として行われます。
このヒアリング内容を基に、どのようなWebサイトを制作するのか、その基本方針が決まってきます。
では、具体的にヒアリングを行う目的としてどのようなものがあるのでしょうか?
現状と問題の把握
ヒアリングの目的の1つ目は、現状と問題の把握です。
クライアントがどういう方なのか、どのような事業をされているのか現状を把握します。
その中で、現在どういう悩みを抱えているのか、今後どのような目標があるのか等Webサイトに限らずクライアントが行っている事業そのものについてしっかり把握します。
そして、クライアントの事業全体の課題や目標を整理するなかで、Webサイトによってどの範囲をどのようにアプローチしていくのか戦略を立てていきます。
これにより、主軸となるWebサイトによる事業目標を明確にしていきます。
要望の把握
ヒアリングの目的の2つ目は、要望の把握です。
クライアントがWebサイトに求めている機能や要件を明確にしていきます。
お問合せフォームやECサービス、ブログ機能などWebサイトに盛り込みたい機能と何故その機能が必要なのかについて把握します。
さらに、サーバー環境の制約やロゴや企業カラーなど必ず使用して欲しい要件なども具体的に聞き出すようにしておきます。
この内容と、前述したWebサイトによる事業目標を踏まえて、Webサイトの仕様やコンテンツを考えていきます。
認識の共有
ヒアリングの目的の3つ目は、認識の共有です。
クライアントがイメージしている雰囲気を具体的な表現に置き換えていきます。
例えば「お洒落なデザインがいい。」という要望に対し、どういった色やフォントスタイル等をイメージしているのか、参考サイトなどを見ながらお互いの認識を可視化していきます。
これにより、デザイン案ができた際に認識の齟齬による作業のやり直しを防ぐことができます。
ヒアリングシートを活用するメリット
ヒアリングを行う上では、ヒアリングシートを活用すると効果的です。
ヒアリングシートを活用するメリットについて紹介します!
ヒアリングをスムーズに行うことができ、確認漏れの防止になる
ヒアリングシートが無い状態で、クライアントとの打ち合わせに臨むとどうなるでしょうか?
質問の順番がバラバラになったり、何を聞くのか忘れてしまったり、確認しておくべきことを漏らしてしまったりすると思います。
ヒアリングをスムーズに行い、確認すべきことを聞き漏らさないためにもヒアリングシートを作成しておくことが重要です。
不要なやり取りを防止できる
ヒアリングシートが無い場合、メールや電話で何度もやり取りをすることになり、手間がかかってしまいます。
クライアントも忙しい中、何度も対応することになると不満に感じるかもしれません。
ヒアリングシートを活用することで、不要なやり取りを防止することができ、結果としてクライアントの満足度の向上にもつながります。
他の案件でも活用できる
作成して活用し、改善を加えたヒアリングシートは他の案件でも活用できます。
自身が使用するだけではなく、スタッフ間で共有することで、ヒアリングの品質を均一化することにもつながります。
また、ヒアリング方法がわからない新人社員の教育にも活用できます。
ヒアリングの進め方
Web制作の依頼を受けた後の初回ヒアリングの進め方について紹介します。
あくまで基本的な一例なので、クライアントに合わせて進め方を調整してください。
ヒアリングシートの作成
ヒアリングを行う際は、事前にヒアリングシートを準備しておきましょう。
ヒアリングシートを作成するにあたって、まずはWeb制作を考えるにあたって何を把握しておきたいかを書き出してみます。
そして、その把握したい内容に対応する質問項目を考えていくことで、過不足なく適切なヒアリング事項を揃えていくことができます。
なお、質問事項はクライアントが答えやすい質問文に置き換えることも重要です。
ヒアリングシートは、クライアントや制作チームが見ても分かるよう、把握事項をジャンル分けして何を把握するための質問なのか分かるようにレイアウトしておきましょう。
ヒアリングシートに掲載すべき項目は、この後まとめて詳しく解説します!
ヒアリングシートの事前送付
ヒアリング当日は、打ち合わせ時間が限られており予定通り話が進むとは限りません。
そのため、事前にヒアリングシートを送付し、可能であれば回答を送っていただくと当日のヒアリングがスムーズに進みます。
事前送付により、クライアントも必要な情報を事前に整理することができます。
また、事前に両者の共通認識を多くもっておくことで、ヒアリング当日には、この回答を基により一歩踏み込んだ質問をすることができます。
これにより、より具体的なWebサイトの構成を考えていくことが可能となります。
クライアントが忙しい場合は、ヒアリングシートの送付のみ、または部分的な回答をお願いするなど配慮し、双方にとって実りあるヒアリングとなるよう調整します。
ヒアリングの実施
ヒアリング当日は、初顔合わせの場合も多いため、簡単なアイスブレイクを挟んだ後にヒアリングに進むと円滑に話を進めることができます。
また、一方的に質問をするのではなく、相槌や内容の深掘りを行いながら、お互いの信頼関係を深めていくことも重要です。
ヒアリングは、ヒアリングシートの項目を網羅できるよう時間配分をして話を進めていきます。
なかなか具体的な回答を得られない場合は、質問内容を変えてクライアントに寄り添った対応を心がけましょう。
ヒアリング内容の整理・分析
ヒアリングで回答しただいた内容は、クライアントや制作チームで共通認識を持つことができるよう整理し共有します。
さらに、このヒアリング内容をそのままWeb制作に反映させるのではなく、内容を分析してクライアント自身が気づいていない潜在的な課題や価値なども探りながら、Webサイトの目的や課題解決に向けたアプローチ方法をまとめていきます。
そして、これをもとにWebサイトの構成を企画し、クライアントに提案を行う準備を進めていきます。
ヒアリングシートに掲載すべき項目とは?
それでは、ヒアリングシートにはどのような項目を掲載するべきでしょうか?
カテゴリー毎に詳しく紹介します!
クライアントの基本情報について
まずは、クライアントの基本情報について、下記の項目を確認するようにしましょう。
自身で調べてわかるものについては、事前に記入しておきましょう。
- 会社名
- 代表者名
- 担当者名
- 電話番号
- メールアドレス
- 決裁者
- 担当者のWebリテラシー
決裁者は、担当者なのか事業部長なのか社長なのか、誰が最終判断を下すのかを確認しておきましょう。
決裁者が社長の場合、ワイヤーフレームやデザインの段階で担当者だけではなく、社長にも確認を依頼する必要があります。
Webサイトが完成してから初めて社長に確認を依頼すると、思ったものと違った場合、例えばデザインからやり直すといったことが起きてしまうかもしれません。
また、担当者の方に合わせて、説明の仕方や進行方法を考えていくためにも、担当者のWebリテラシーについても事前に確認しておくと良いです。
クライアントの事業について
次にクライアントの事業を把握するために、下記を確認しましょう。
- 事業内容
- 競合他社
- 事業の目標
- 現在抱えている問題
- 既存サイト・広報の手段
それぞれについて詳しく解説します!
事業内容
クライアントやクライアントの事業内容について把握します。
事業内容は、特徴や強みのみならず、伸び悩んでいる点や不安要因等の弱みについても尋ね、事業全体を俯瞰的に把握するようにしましょう。
売上の推移や顧客満足度など、数値データで状況を把握できる資料も共有していただける場合は、押さえておきましょう。
また、現在の事業内容に至るまでの苦労話なども知ることで、クライアント自身も気づいていないサービスや商品の魅力を見つけ出すヒントとなります。
競合他社
競合他社について、どのような企業があるのか、クライアント企業と競合他社でどのような違いがあるのかを把握します。
また、現在のお客様は競合他社ではなく「なぜ御社を選んでいるか」の理由を聞くことで、その理由がWebサイトのコンテンツ制作のヒントになるかもしれません。
競合他社について、ヒアリング後に、どのようなWeb施策を行っているか確認しておくようにしましょう。
事業の目標
現在の事業を今後どのように展開していきたいのか、今後の目標について把握します。
短期的、中期的、長期的な目標と分けて質問することで、より具体的な目標を把握することが可能です。
目標の売上額やお問合せ数など数値で把握できる目標もあるか確認してみましょう。
現在抱えている問題
現在クライアントが抱えている問題について把握します。
事業の業績についてなのか、新たな事業展開について、ブランディングについて、採用活動等、多方面について悩みを聞き出し、これらを順位付けできるよう問題の深刻度合いについても把握できるようにします。
既存サイト・広報手段の確認
既存サイトの有無について確認します。また、現在の広報ツールとして何を使っているのかについても把握します。
パンフレットやチラシ、SNS、ブログなど紙媒体からデジタル媒体に至るまで活用している媒体を確認します。
さらに、Webサイトのアクセス解析データがあれば、権限を共有いただくようにしましょう。
Webサイトのコンセプトについて
次にWebサイトのコンセプトを定めるために、下記を確認しましょう。
- Webサイトの目的
- Webサイトに期待する効果
- ターゲット層
それぞれについて詳しく解説します!
Webサイトの目的
Webサイトを作る目的について把握します。そもそも何故Webサイトの制作依頼をしたのか、その動機を丁寧に聞きましょう。
そして、事業の課題や目標と照らし合わせながら、Webサイトによってどのような目的を達成しどのような事業成果に繋げていきたいか具体的に考えていきます。
Webサイトの目的について例えば下記のようなものがあります。クライアントが回答につまる場合は、この中からどれが一番近いかを確認するようにしましょう。
- 企業広報
- 商品や製品の認知向上
- 商品や製品の販売
- 新規採用の強化
- 投資家向け情報の発信
Webサイトに期待する効果
Webサイトによってどのような変化・効果を期待するかを把握します。
具体的には、サービスの認知度向上やお問い合わせ件数の増加、会員登録の増加などがあります。
これにより、Webサイトの目的達成を評価するための具体的な指標を明確にしていきます。
ターゲット層
制作したWebサイトにアクセスして欲しいターゲット層を把握します。
ターゲット層は、下記のような具体的な属性を定めてどのような人物像かを考えていきます。
- 年齢
- 性別
- 居住地域
- 職業
- 役職
- 収入
- 家族構成
- 趣味
対消費者向けの事業か、対企業向けの事業かによって、押さえておくべき項目が変わるので注意が必要です。
Webサイトのコンテンツについて
次にWebサイトのコンテンツ制作について、下記を確認しましょう。
- 掲載したいコンテンツ
- ロゴ、ブランドカラー、素材提供の有無
- 指定フォントの有無
- 必要な機能
- 撮影の有無
- SNSとの連動
- 言語対応
それぞれについて詳しく解説します!
掲載したいコンテンツ
Webサイトにどのようなコンテンツを掲載したいか把握します。
事業コンセプトや商品紹介、事例紹介、採用情報、ブログ記事、セミナー案内など、必要なコンテンツの種類とその優先順位、ボリュームについて尋ねます。
ロゴ、ブランドカラー、素材提供の有無
クライアントが所有するロゴやブランドカラー、Webサイトで使用するための画像や素材を把握します。
これにより、Webサイトのデザインをクライアントのブランドイメージに合わせることができます。
ブランドガイドラインがある場合は、事前に共有いただくようにしましょう。
特に、ロゴについては、余白や最小サイズなど使用ルールが厳格な場合があるのでしっかりと確認しておきましょう。
指定フォントの有無
Webサイトに使用するフォントについて指定がないかを把握します。
こちらもロゴと同様にブランドガイドラインがある場合は、指定されている場合があるので注意しましょう。
必要な機能
クライアントがWebサイトに組み込みたい具体的な機能や機能要件を把握します。
例えば、問い合わせフォームやショッピングカート、ユーザー登録機能、メルマガの購読機能などが含まれます。
これにより、Webサイトの開発に必要な機能を特定し、実装することができます。
撮影の有無
Webサイトに使用する画像や動画などの素材をプロのカメラマンなどに依頼する必要があるかどうかを把握します。
必要な場合は、撮影の計画や予算を全体の業務工程・予算に組み込んでいきます。
SNSとの連動
既存のSNSや新規SNSと連動させるかどうかを把握します。
どのSNSと連動させたいのか、その投稿をどのように表示させたいのか等の要望についても確認します。
言語対応
日本語だけではなく、多言語対応が必要かどうかを把握します。
多言語対応が必要な場合、言語ごとのコンテンツ管理や翻訳の手配、多言語化ツールなどを検討します。
Webサイトの仕様について
次にWebサイトの仕様ついて、下記を確認しましょう。
- 対応OS・ブラウザ・デバイス
- CMSの導入
- サーバー・ドメインの有無
- セキュリティ対策
それぞれについて詳しく解説します!
対応OS・ブラウザ・デバイス
Webサイトの対象とする主要なOSやブラウザ、デバイスを把握します。
ターゲット層がストレスなくWebサイトを閲覧・操作できるよう、ターゲット層のシェア率を調べ、これに最適化した組み合わせを考えていきます。
CMSの導入
クライアントがWebサイトを管理するために使用したいCMS(コンテンツ管理システム)の導入の必要性を把握します。
どのようなコンテンツ管理・運営をしたいかを聞きながらCMS導入の必要性を検討していきます。
最近ではWordPressが多く使われていますが、クライアントにはCMSのメリット・デメリットを分かりやすく説明したうえで導入を検討していきましょう。
また、企業によっては、WordPressの使用がNGの場合があるので、事前に確認しておきましょう。
サーバー・ドメインの有無
クライアントが既に所有しているサーバーやドメインがあるかどうかを把握します。
これにより、Webサイトのサーバー環境やドメイン設定に関する要件を確認し、適切な手続きを行うことができます。
セキュリティ対策
クライアントが必要とするセキュリティ対策を把握します。
具体的には、SSL証明書の導入、フォームからのスパム防止策、不正アクセス防止策などが含まれます。これにより、Webサイトのセキュリティを確保するための適切な対策を検討していきます。
提供いただける資料について
次に提供いただける資料についてどのようなものがあるかを確認します。
例えば、下記のようなものをいただいておくと、Webサイトのコンテンツに活用できるかもしれません。
- 会社案内
- パンフレット
- リーフレット
- カタログ
- 広告
- 求人票
- 商品や製品の現物
- 商品や製品の画像データ
- 商品や製品の説明書・仕様書
- 商品や製品に関するお客様の声
制作進行について
次にWebサイトの制作進行について、下記を確認しましょう。
- 予算・希望価格
- 希望公開日・スケジュール
- 主な連絡手段
それぞれについて詳しく解説します!
予算・希望価格
Webサイト制作に関する予算や希望価格を把握します。
これにより、Web制作業務の範囲や機能の決定、開発リソースの割り当てなどを適切に計画し、クライアントの予算に合った提案を検討していきます。
提案にあたって増額が必要な場合は、その根拠を丁寧に説明し、必要性の有無を検討してもらいます。
希望公開日・スケジュール
Webサイトを公開する希望日やスケジュールを把握します。
素材を提供していただく場合は、いつ頃に提供可能かも確認します。
これにより、Web制作の進捗管理やタイムラインの調整を行い、クライアントの要望に合わせたスケジュールを確保できるよう検討します。
主な連絡手段
クライアントとのコミュニケーションに使用する主な連絡手段(メール、電話、オンラインチャットなど)を把握します。
これにより、行き違いのない円滑なコミュニケーションが可能となります。
運用・保守について
次にWebサイトの運用・保守ついて、下記を確認しましょう。
- 更新頻度
- SEO対策
- サポートの必要性
それぞれについて詳しく解説します!
更新頻度
Webサイト制作後に、クライアントがどのコンテンツをどのくらいの頻度で更新するかを把握します。
これに合わせて、Webサイトの仕様を計画するとともに、運用・保守サポート内容の提案を考えることができます。
SEO対策
SEO対策の要件や目標を把握します。
これにより、適切なキーワードの選定、メタタグの最適化など、Webサイトの検索順位向上をサポートする対策を検討します。
サポートの必要性
Webサイトの制作後に運用・保守のサポートが必要かどうか、必要な場合のサポート要件や範囲を把握します。
サポート内容には、アクセス解析、SEO対策、バグ修正や機能追加のサポート、定期的なバックアップなどが含まれます。適切なサポート体制を確保し、目的達成に効果的なWebサイトの運営と改善を支援します。
ヒアリング時の注意事項
ここまで、ヒアリングシートに掲載するべき項目について紹介してきました。
最後にヒアリングを行う時の注意事項について解説します!
クライアントに寄り添ったヒアリングを行いましょう!
クライアントに応じたヒアリングをすること
まず1番重要なのは、クライアントに応じたヒアリングを行うことです。
紹介したヒアリングシートの項目をすべてクライアントに丸投げしても上手く回答を得られないでしょう。
クライアントのWebリテラシーに応じて、質問の方法を変えてみたり、選択式にしてみたりといった配慮が必要です。
なるべく専門的な用語は使わずにクライアントに寄り添ってヒアリングをするようにしましょう。
受け身でヒアリングしないこと
次に重要なのが受け身でヒアリングを行わないことです。
例えば、Webサイトのコンテンツ内容について全てクライアントからのヒアリングで決めるのではなく、こちらから提案することも重要です。
他にも、「CMSは必要ですか?」とただ聞くのではなく、「どのくらいの頻度でどのくらいの量の更新が発生しそうですか?」と聞いた上で、「月に1回程度でしたら、CMSを構築するよりも保守契約で弊社に更新を依頼した方が、◯◯なのでお得ですよ。」のようにヒアリングをした上で、選択肢を用意して提案するなどが必要です。
ただ受け身で聞くのではなく、クライアントが答えやすいように情報を提供することも心がけましょう。
まとめ
ヒアリングで聞き取った内容から、しっかり情報を整理、分析することで目的達成につながる効果的なWebサイトを計画することができます。
また、クライアントから知りたい情報を的確に聞き出すためには、コミュニケーション能力が欠かせません。
特に初回ヒアリングは、戸惑うことも多く、予定時間内に全てを把握するのはなかなか難しいかもしれません。
そのため、ヒアリングシートを作成して事前準備をしっかりしておくことが重要です。
そして、クライアントに真摯に寄り添い話を聞くことで、良い信頼関係を築き、お互いにとって有意義なヒアリングとなるようにしていきましょう。
この記事の内容をまとめたヒアリングシートを配布しています
ヒアリング時に確認すべきことをまとめたヒアリングシートを作成しました。このシートを活用してぜひ良いヒアリングを行ってください。
Excelでも配布していますので、自社向けにアレンジいただくのも良いですね。
以下のボタンから資料をダウンロードしてご活用ください!